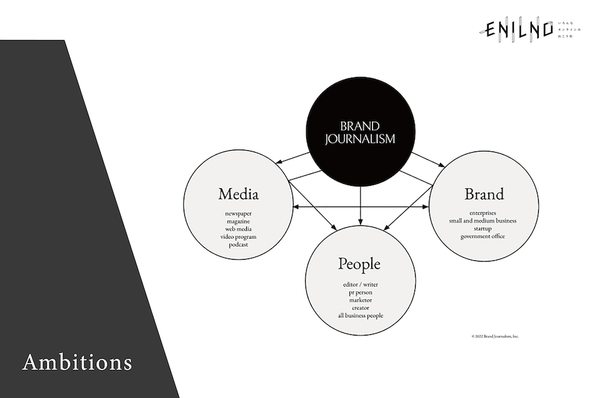ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。
これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。
「慣行農業が99.5%」の日本に新たな価値を。水耕栽培×水産養殖の循環型農業「アクアポニックス」が持つ可能性

「アクアポニックスは水耕栽培と水産養殖をかけあわせた循環型農業です。慣行農業と異なる点は、生産性の高さと環境配慮の両立ができるところと、生態系が目に見えるという意味で癒やしやエンタメ効果が高いというところだと考えています」
そう語るのは、アメリカやオーストラリアなどを中心に一定の市民権を得ているアクアポニックスを、日本でも広めようと様々な活動を行っている株式会社アクポニの代表・濱田健吾氏だ。

一般に、慣行農業(栽培)とは各地域で慣行的に行われている農薬や化学肥料を利用した農業のことを指す。他方で近年、国によって推進されているロボットやAI、IoTなどの先端技術を用いた「スマート農業」や持続可能な食料システムの構築に向けて2021年に策定された「みどりの食料システム戦略」は、環境問題・人口減少・食料安全保障といった迫りくる現代社会の課題を解決するためのもの。先人たちが培ってきた知識や知恵、経験を否定するものではないが、これまで行われてきた農業に固執するのではなく、イノベーションを起こす動きだといえる。そんなイノベーティブな農業の1つとして、にわかに注目を集めているのが、アクアポニックスである。
先述したようにアクアポニックスとは、植物の水耕栽培装置と魚等の飼育装置の2つを組み合わせることで、「資源」「エネルギー」「人」「情報」などの循環をつくることができる農業である。基本原理は、魚に与えるエサが魚のフンとなり、それを微生物が分解することで植物の栄養になるというもの。魚と微生物、植物の三者が生態系をつくり、バランスよく循環する〝仕組み〟を整えることができれば、農業としてだけでなく個人で楽しめるものとしても、少しずつ認知度が高まっている。
INDEX
アメリカの農場に飛び込み2年間の〝武者修行〟を経験
濱田氏がアクポニを創業したのは2014年のこと。それまでは、趣味の釣りを通じて知ったアクアポニックスを自宅で個人的に楽しんでいたが、新たな農業としてだけでなくビジネスとしての可能性も感じ、起業を決意。普及活動を始めた。

その後、アクアポニックスを産業として定着させるべく、2017年から約2年間、アメリカ各地のアクアポニックス農場を渡り歩き、その手法を学んできたという。
日本に帰国すると、日本の気候に合ったアクアポニックスのノウハウを蓄積・研究するため、試験用の農場をつくった。「湘南アクポニ農場」と呼ばれるそこでは、「LED型」「太陽光型オフグリッドモデル」「太陽光型点滴栽培」「太陽光型切換モデル」と4つの異なるアクアポニックス設備を見学できる。

さらに、2022年に新設した「ふじさわアクポニビレッジ」では、アクアポニックスの最新型の「縦型水耕システム」と「養殖設備」を組み合わせた3つのサイズの異なるパッケージ農場(アクポニハウス)の見学や、生産管理アプリやIoTセンサーなどを実際に目で見て体感することが可能だ。
この2つの農場は、後述する4つの事業のすべてとつながっている。というのもオンラインやセミナー、あるいはメディアなどを通じて「アクアポニックスとは何か」を座学や知識として伝えること以上に、実際に目で見てもらうこと、体感してもらうことによってアクアポニックスの魅力が伝わるからだ。
「アクアポニックスは生産性の高さと環境負荷の低さが強みではあるものの、エンターテインメント性の強さもその特徴の1つなんです。だから、農園に来てくださった皆さんに循環型農業とはどういうものかや、そこにある生態系を理解してもらったうえで、採れたての新鮮な野菜を食べてもらうことがとても価値のあることだと思っています。やっぱり人は、そうした体験で考え方も変わるし、〝応援したい〟と思ってもらえるようになると感じています」
2021年からの約2年で35農園に拡大
「アクアポニックスで地球と人をHAPPYに」というミッションを掲げるアクポニは、「教育」「農園施工」「生産」「流通」の4つが事業の柱である。
1つ目の「教育」として、具体的には、日本初にして唯一のアクアポニックスが学べる「アクアポニックス・アカデミー」の運営、文部科学省もすすめるSTEAM教育の一環としての教育機関への授業協力などがある。
2つ目の「農園施行」は、先の啓蒙活動を通じてアクアポニックスを知った個人や企業などに向けて、農園を設計・施工の支援を行う事業だ。2021年からの約2年間で35の農園を日本各地につくってきた。ちなみに、その運営のほとんどが、延べ300人もの卒業生を輩出してきた先のアカデミーの卒業生であるという。
3つ目の「生産」の事業とは、自社農場での試験栽培だ。現在の栽培品種は葉物野菜やハーブが中心であるが、付加価値の高いイチゴなども試験栽培に入っている。もう一方の水産としては、ティラピア(イズミダイ)やチョウザメ、モロコ、鯉、ニジマスなどを育てている。

また、アクアポニックスを導入した個人や企業が直面する生産管理における課題に対する支援もおこなっている。2022年10月にリリースした生産管理のための「アクポニ栽培アプリ」も含めたIoTセンサーやデータ管理といったテクノロジーを使って、リモートでの課題解決支援を行っている。具体的には、人が行う作業(行動データ)と、環境制御のデータを記録・集計・レポートすることによって、生産管理に必要な様々なデータが一元管理できるようになるという。
「現状、アクアポニックスは隣近所で教えてもらえるような農業ではありませんので、蓄積されたデータを集約し、みんなで共有していくことで、栽培方法のさらなる改善に役立てていきたいと考えています」
「環境にやさしく、農薬や化学肥料を使わない」という利点が活かされていない
4つ目の事業が流通だ。当然ながら、農業は生産したものを売らなければ利益にはつながらない。現状では、日本においてアクアポニックスでつくられた野菜や魚は認知度が低いことから、慣行農業のものと販売価格に差をつけることが難しい。他方で、アクアポニックスの先進国であるアメリカでは、2〜3倍の値段がつくことも珍しくない。循環型農業として環境にやさしく、さらに農薬や化学肥料を使わない〝安全で美味しいものが生産できること〟が認知されており、そのことがうまく販売価格につながっているからだ。
「そこでは、アクアポニックスという農業のブランディングが不可欠であると考えています」

たとえば日本で最も知名度の高い有機農産物の規格である「有機JASマーク」は、基本的に水耕栽培を対象としていない。そのためアクアポニックスは無農薬、無化学肥料、無除草剤の有機農法ではあるものの、有機JASマークを付すことできない。他方、アメリカのアクアポニックス農家には、USDA(アメリカ合衆国農務省)によるオーガニック認証の取得実績が複数あると言う。
だからこそアクアポニックスという〝集合体〟としてのブランディングと流通網の構築が欠かせないと濱田氏は語る。

「今から5年を目処に、アクアポニックスの農場を200まで広げていきます。スケールが広がることによってブランディングも含めた流通に関するソリューションも確立できると考えています。ただ、既存の野菜のように地方でつくった野菜をトラックで都会に輸送するような流通ではなく、地産地消が原則にあります」
「慣行農業が99.5%の日本」にアクアポニックスが貢献できること
SDGsを含め環境意識の高まりや企業の社会的責任が社会に浸透してきたことは、ここ数年のアクポニ躍進の追い風要因になっていることは間違いない。では、アクアポニックスは具体的にどのように環境面でのメリットがあるのだろうか。
「環境面については、水とエネルギーと肥料の利用効率が上がるというメリットがあると考えています。特に水に関しては、土耕栽培と比べて80%以上も節水できるとも言われています。これまで日本でアクアポニックスの訴求力が弱かった理由はここにあったのかなと思っています。というのも日本は気候的に水が豊富ですので。ただ、一方ではマクロの課題として肥料価格の高騰という課題が出てきています。アクアポニックスは、魚の排泄物を微生物が分解し、植物がそれを栄養として吸収し、浄化された水が再び魚の水槽へと戻るという生産システムです。言い換えれば肥料生産にかかるエネルギー効率がとてもよく(温室効果ガス72%減)、環境負荷を減らすことができるんです」
加えて、土壌汚染対策としても利点があると濱田氏。
「土壌汚染につながるような農薬を使わずに栽培できますし、農場から排水や廃棄物を出さないようにすることも可能です。ですので、農場周辺の環境へ悪影響を及ぼさないという意味でメリットがあります。これらの価値を合わせると、アクアポニックスは単なる生産システムではなく、資源やエネルギーの循環をつくるコアパーツになり得ます。さまざまな循環技術やテクノロジーの集合知として活用し、これから先も進化させ続けていくことで、大きな価値を生み出すと考えています」
ただ、アクアポニックスのようなイノベーティブな農業が日本で大きなムーブメントになるには、いくつかのハードルを乗り越えなくてはならないと濱田氏は考えている。1つはITと農業の両方に詳しい人材が少ないということ。

「農業現場を理解している先端技術の開発者がほとんどいないこと、農業従事者のなかにITに長けている人が少ないことは課題として挙げられると思います。加えていえば、ITと農業だけでなく、そこにビジネス知識も掛け合わせることができる人材が増えてくると、アクアポニックスだけでなく、日本の農業全体がより良くなっていくのではないでしょうか」
さらに、日本人一人ひとりの消費意欲の多様性の低さもハードルに感じている。
「アメリカに住んでいるときにすごく実感したことですが、個人の消費にすごく多様性があるんです。値段が高くても地元産なら買うとか、安全性が高い野菜なら高くてもあたりまえとか、そういった層が結構な割合でいます。一方で、日本だと割と野菜に対する消費意欲は画一的で、多くの人が『安ければ安いほどいい』『一年中、品物が揃っている』『安全なのが当たり前』という3つが根底にある。そういう意味では、個人の消費者の意識も変わっていかないと、99.5%が慣行農業という現状は変わっていかないのだと思います。農家さんは、どうしたってお客さんである消費者が求めるものをつくるわけですから」
すでに途中で触れたように、アクアポニックスは農場のなかで生態系が成り立ち、循環している農業であり、その様子が目に見てわかりやすくなっている。これは、言い換えれば消費者の意識を変えやすい農業であるともいえる。アクアポニックスには、小さな空きスペースを使って行うことができるというもう一つの特徴もある。そのため商業施設や都市部の空きスペース、あるいは学校や家庭などで、環境教育や食育の観点から設置することも可能なのだ。そういった意味では、アクアポニックスに限らずとも、イノベーティブな農業を普及させる起爆剤的な存在にもなり得るのかもしれない。
濱田健吾
Kengo Hamada株式会社アクポニ代表取締役
宮崎県出身。大学卒業後、オーストラリアでの日本語教師を2年間務めたのち、専門商社に入社。新規事業開発を担当し、シンガポールで中古車買取事業やロシアで化粧品ブランド立上げの新規事業を企画、事業展開。その後アマゾンジャパンを経て、アグリイノベーション大学校で有機農業を学ぶ。2014年4月にアクポニ(旧・おうち菜園)を創業。2017年からの約2年間はアクアポニックスが誕生したアメリカの農園で学ぶ。