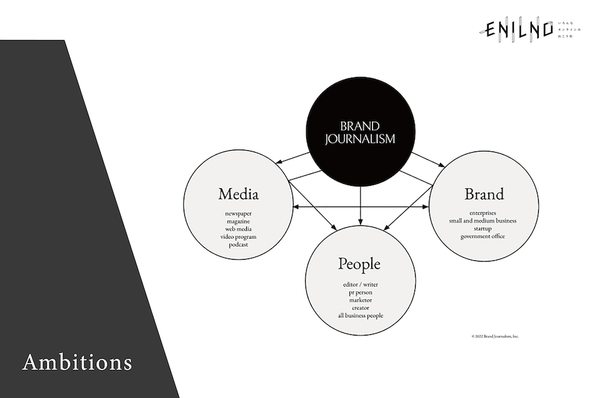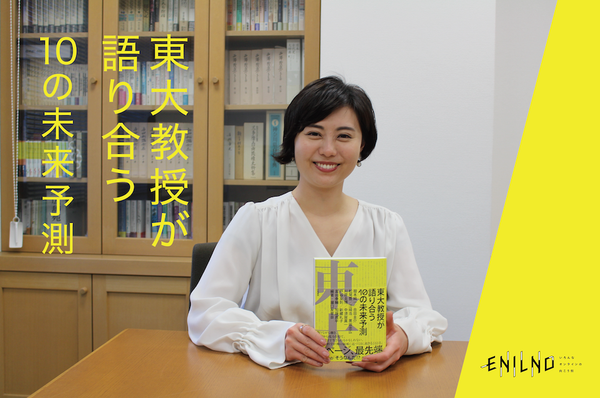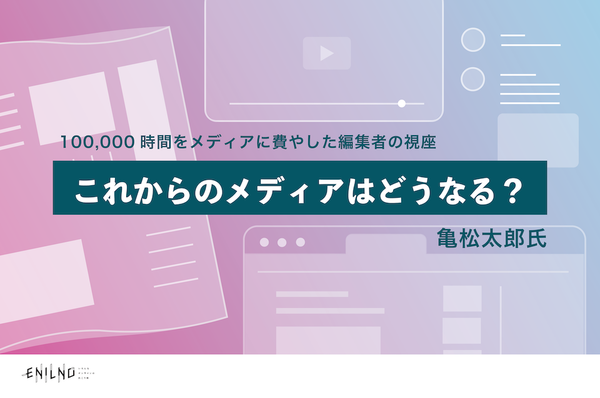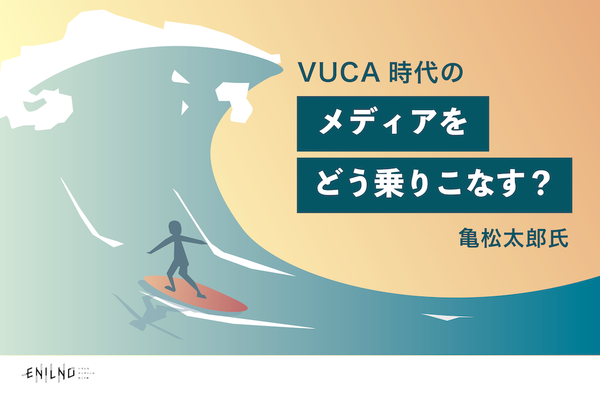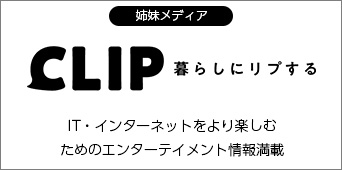ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。
これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。
病気や障がいなどによる外出困難者が活躍。分身ロボットカフェが目指す近未来

2022年8月、米Amazonがロボット掃除機「ルンバ」で知られるiRobotを買収すると発表したのは記憶に新しい。
ひとくちにロボットといっても、ルンバのように実用性に特化したロボットもあれば、人とコミュニケーションを図り癒しを与えるaiboやBOCCO、接客活用可能なPepper、応接室のドアを開けてお茶を運ぶニョッキーなど、人工知能を搭載し、感情を読み取り学習しながら動くロボットもある。
遠隔操作して動かす人型の分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」は、一見して後者に属するロボットだが、実はそのどちらにも属さない。オリヒメは心身の病気や障がいを持った人をはじめ、家族の介護など家庭の事情があって自宅にいなければならない人など、いわゆる“外出困難者”の分身を担うロボットだ。

そんなオリヒメを活用したカフェ「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」が東京・日本橋エリアにオープンして、1年が経った。外出困難者がどのように活躍しているのか、オリィ研究所の広報・濱口敬子氏に話を聞いた。
操縦者と一心同体になって働くOriHime。AI未搭載のそのワケは?
ロボットと聞くと機械学習を行い、人からの指示を出さなくても自律的に認識し、最適なアクションを行うイメージがあるが、オリヒメ自体に人工知能(AI)は搭載されていない。
あくまでも操縦者(パイロット)の分身として、パイロットの意思を反映したコミュニケーションを図ることが目的として存在するのがオリヒメだ。ヒトの型に似た、ヒトの器ということになる。

「オリヒメはAIを搭載していない、人が操作する前提のロボット。パイロットの意思で動かしているから、人の意思を介在しないと動かないのが特徴です。パイロットからは相手の顔が見えているので、その場にはいないけれどその場にいるのと同じ状態。自分で見たい方向に向きを変えることもできますし、ゼスチャーボタンで反応もできます」と濱口氏。
オリヒメに内蔵されているスピーカーを通して自身の声を届けることもできるため、対面する相手はロボットではなく人とコミュニケーションをとっているとしっかり認識できる。
「ネット環境が整っていればパソコンひとつ、スマホひとつで誰でも操縦できます。ALSなどで身体が動かない人はOriHime eye+Switchという視線入力装置を活用して文字入力を行い、意思伝達を図れます。これまで社会に参画したくてもできなかった、さまざまな外出困難者たちみなさんにご活用いただけます」(濱口氏)
社会経験がなくても接客可能に。OriHimeが実現した心理的安全性を担保した働き方
そんなオリヒメを活用したカフェ「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」だが、なぜ外出困難者の活躍の場をカフェにしたのだろうか。そして、社会経験の少ない外出困難者が、いきなり接客を伴う働きをすることは可能なのだろうか。
「特別支援学校などを卒業したての方々は、アルバイト未経験者も少なくありません。そのため、社会経験が少なくても業務内容が想像しやすい“カフェの接客業”を設定。まずは“ドリンクを運ぶ”などのイメージしやすい仕事から始めてみることになりました。
接客面に関しては、接客業に向いているか面接でコミュニケーションスキルを見た上で、まずはご本人の意欲を重視しています。採用後も接客とコミュニケーションの研修をしています。もし、業務でミスが発生した際、パイロットはオリヒメを介してごめんなさいのポーズをしたりして気持ちを表現することができます。お客さんにとって、それがどこか愛らしく感じられたりもするようです」(濱口氏)

また、オリヒメはコミュニケーションを図るロボットのため、このカフェの業務では「客と話をする」ことがメイン。客がオリヒメを介してオーダーした後、メニューが届くまで会話をしているという。
初対面の客としばらくの間話さないといけないのは、たとえ社会経験が豊富でも難しい。ところが、外出困難者であるパイロットたちは、意外にも会話が弾んでいることが多いという。
「生身の人間相手だと緊張してしまうところ、お客さんからしたらオリヒメしか見えないので、ロボット相手で話しやすいようです。パイロット側も心理的安全性を担保されているなかで話せるので、楽しく話せるのかもしれません」(濱口氏)
また、ロボットなのに失敗する可能性があるところもオリヒメの人間らしい魅力のひとつ。
「AI搭載ロボットならミスなどないのでしょうけど、オリヒメはあくまでも人が操作しているのでミスも発生します。配膳テーブルを間違えたり、コーヒーの粉をこぼしたりして、慌てているロボットの様子がどこか人間味があり、その様子を見たお客様も楽しそうなんです。
ロボットは完璧なイメージがあるからこそ、イレギュラーなことが発生した際にはトラブルがショーに変わるんですよね。ですから、接客がそつなく終わるとエンジニアとしては安心だし満足だけど、お客さんはなんだか普通だよねという感想を抱かれる。ミスをしないに越したことはありませんが、とてもハートフルなカフェになったと自負しています」(濱口氏)

このように心理的安全性が担保されている中、パイロットは失敗したり学んだりしながらコミュニケーションスキルを上達させていく。最近では、そのコミュニケーションスキルを買われ、客として来店した経営者にスカウトや引き抜きをされるパイロットも増えたという。
「和歌山のアドベンチャーワールドのレストラン入り口で、ご案内業務をするパイロットや、大手企業の受付をするパイロットなど、オリヒメを介してカフェの店員以外の活躍の場を広げているパイロットも増えました。外出困難者の可能性が広がっていくのを嬉しく思います」と濱口氏。
現在在籍するパイロットは70名以上。同カフェで働きたいと思っているパイロットはまだまだ多く、全て採用することは難しいのが現状だ。濱口氏は「SDGs観点でオリヒメを活用してくれる企業も多いのですが、コロナでオフラインでの交流が憚られる今こそ、もっとオリヒメで働くことを視野に入れてもらえたら」と話す。
コロナ禍でリアルの価値が上がったが、アフターコロナになっても外出困難者の状況は変わらない。オリヒメはそんな人たちの、希望の星として今後も活躍していくに違いない。
濱口 敬子
Keiko Hamaguchi株式会社 オリィ研究所 所長室・広報
広告業界からお米ギフトのEC「八代目儀兵衛」を経て、現在、リレーションテックを掲げる㈱オリィ研究所で広報を担当。