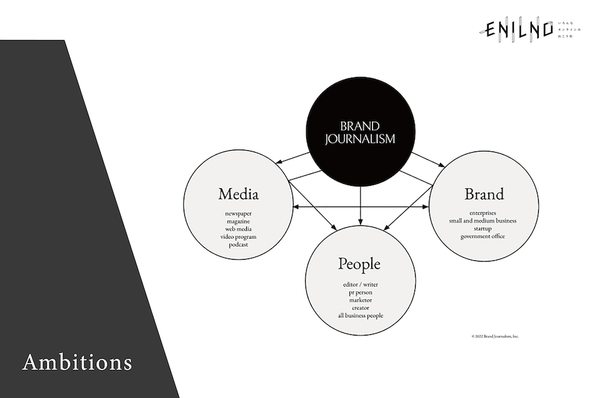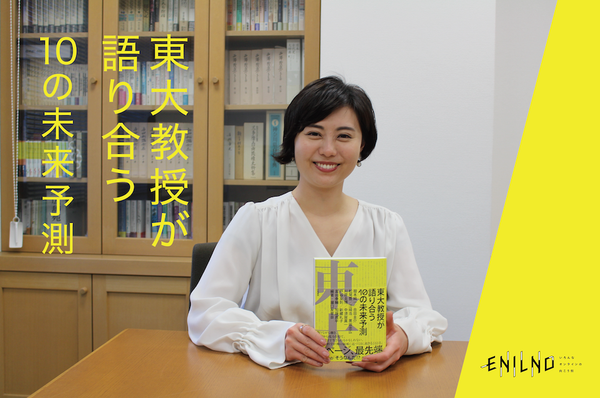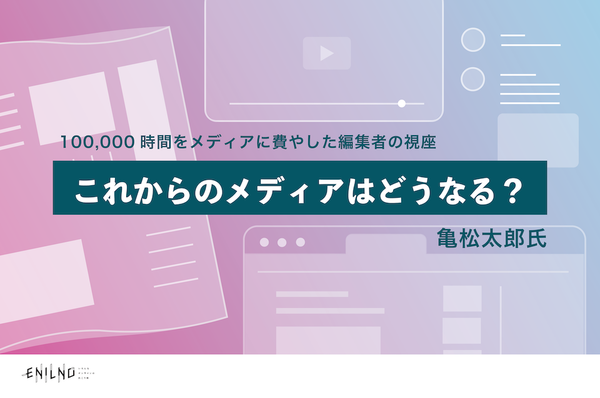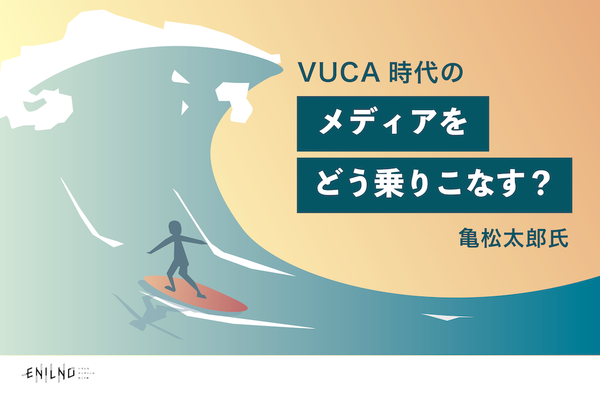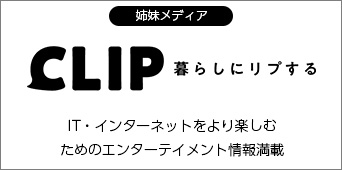ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。
これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。
サブスク関連トラブルの相談は年間55,000件! 今、サブスク市場に起きていること

暮らしにすっかり浸透したサブスク(サブスクリプション)サービス。便利な反面、契約しているサービスや毎月の支払い額をきちんと把握できていない、といった声は多い。そうした契約中のサブスクをAIで自動検知し、一元管理できるツールが「SubFi(サブファイ)」だ。使っていないサブスクはもちろん、気づかずに契約していたサブスクも発見でき、増加するサブスク関連のトラブル防止にも一役買っている。サブスク市場はこれからどこへ向かうのか? サブスク市場の動向とサービスの未来について、SubFiを運営する株式会社renue代表の山本悠介氏に話を聞いた。
年間推計約5,735億円が無駄なサブスクに支払われている

ソニー損保が実施した調査によれば、日本人が“無駄なサブスク”に支払っている金額は年間で推計約5,735億円。確かに、動画配信サービスを数種加入しているものの、実際によく観ているのは1種だけ、というのはよくある話だ。SubFiを使えば、そうした契約中のサブスクをAIで自動検知し、契約・支払いや状況を一手に管理することができる。登録したサブスクは、更新日や支払い状況が自動でリマインドされる。心配事やトラブルがあれば、サブスクに特化した個別相談サービスも受けられる。「実家の両親が使えるようなサービスを目指しています」と山本氏が言うように、サブスクに特化し機能を限定したシンプルさが売りだ。
ITコンサルやITベンチャー企業で、金融システムやWebサービス構築のバックグラウンドをもつ山本氏。ITと金融にあかるい同氏ですら、既存の家計簿アプリを使いこなせてはいなかったと話す。一般的にそうしたツールは、日々の支出入から資産運用まで細かく管理できる反面、レシートを見ながら毎日の支出入を打ち込む必要があり、その作業は膨大だ。特に、サブスクのような自動で引き落とされる固定支出に関しては、管理しようにもそもそも存在を思い出せないこともある。ITサービスに慣れていない高齢者やもともと財務管理が苦手な人ともなれば、そのハードルはさらに高い。

「実家の両親が、携帯ショップや家電量販店などで勧められるがままにWebサービスに加入しており、ほとんど使っていないのに毎月数万円支払っている、という事態に気づきまして。そうした “変な固定支出”だけでもチェックできるツールがあれば良いのに、という思いがサービスの出発点になりました」
SubFiは全国2,000以上の金融機関と繋がっている家計簿ツールとシステム連携しており、口座情報の内の出金データだけを活用している。その中からサブスクへの固定支出だけをAIが自動検知で振り分け、どこにいくら支払いが発生しているのか? 更新・解約のタイミングは? といった契約状況を提示してくれる。
サブスクを利用する人はお気づきだと思うが、サブスクの引き落としというのは、明細上はサービス名になっていないことがほとんど。使っているクレジットカードや決済サービスや銀行によって名称は様々だが、AIがその名称や引き落とし頻度などのビッグデータから予想する。今後データが増えるに従い、予測の精度も上がる見込みだ。
市場に溢れる怪しいサブスク
“忘れていた”サブスクは確かにお金の無駄だが、それ以上に問題なのは“契約した覚えのない”もしくは“解約したいのにできない”サブスクだ。こうした違法ではないが詐欺まがいのサブスクが今、市場に溢れているという。
「例えば、加入時や初月はキャンペーンで無料ですが、加入後は何の連絡もなしに気づいたら課金されている、月額使用料は高く1年間は解約できない……などというのは、サブスク含めWebサービスの世界ではよくある手法です。こうした契約・解約条件は法律上、利用規約に記す必要がありますが、弁護士でもなければ隅々まで読む人はなかなかいませんし、あえてわかりにくく書かれている場合も多いです」
国⺠生活センターがまとめた定期購入やサブスクに関する相談件数は増え、2015年で約5,000件だったものが、2020年には55,000件を超え約11倍になっている。近年の特徴として、ターゲットになるのはWebサービスに慣れ親しむ高齢者だ。
「以前はウェブサービスに弱いといわれていた高齢者ですが、今では多くの方がLINEやInstagram などといった10年ほど前からあるサービスは使いこなしていいる。SubFiのユーザーも50〜60代が全体の2割を占めています」
サブスク離れで善良な事業者も苦戦
コロナ禍に一気に浸透したサブスクだが、こうした現状から事業者側に摘発が入り、また消費者のサブスク離れが進んでいるという。消費者庁は2022年6月1日に改正特定商取引法を施行。悪質なサブスク商法への対策を盛り込んだもので、申し込み最終確認画面に解約条件などの6項目の表示を義務づけた。それでも、これに則ったサービスが100%というわけではないのが現状だ。
悪徳商法のイメージが先行し、善良な事業者もサービスを売りにくくなっている。サブスクは「健全なサービスかどうかを自ら判断できる、情報リテラシーの高い層にしか売れない業界になりつつある」と山本氏。一方で、情報リテラシーのハードルを下げ、広く世間の信頼を獲得するには、テレビCMや店頭PRを展開するなど、大きなコストが必要になる。
それでもサブスク市場は6兆円
今後5〜10年間で、サブスク市場はどうなっていくのか? 山本氏は、コロナ禍がサブスクに過度な期待がもたれた「ピーク」だったとすれば、今は「幻滅期」だと指摘する。
「様々なトラブルが起こり、サブスクから距離をとる消費者は増えています。とはいえ、電気や水道と同じ生活インフラとして、必須に感じる層も変わらず多い。このことから、サブスク市場が急に衰退することはなく、しばらくは横ばいだと思います」
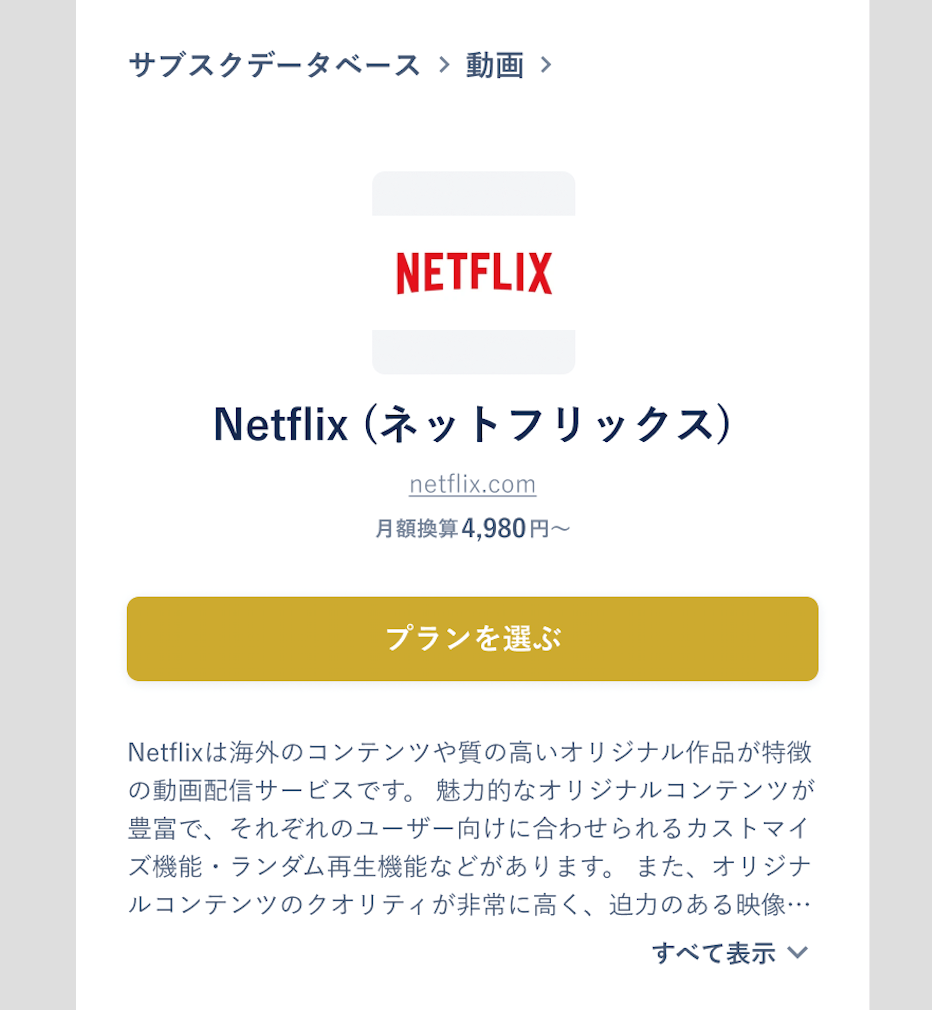
矢野経済研究所は、国内BtoCサブスクの市場規模は2019年で1.1兆円、2023年には3,000億円増の1.4兆円に達すると予測。ベイカレント・コンサルティングの試算では、ここにBtoB領域を加えると、市場規模は2023年に6兆円に達することが見込まれている。一方では今後、消費者のサブスクを見る目も徐々に鍛えられると山本氏。
「今後3年くらいは、事業者は良いサービス作りに尽力し、悪いサービスは徐々に淘汰されるのでは。2025年頃には優良サービスが溢れ、サブスク市場は一気に伸びるのではと思います」
SubFiでは、今後サブスクに特化したECサイトを本格的にローンチする予定。審査の元、優良サービスのみを掲載し、契約・解約などの条件も明記する。
悪質手法が一掃され、品質の良いサブスクが市場を凌駕する時代。その時広がっているのは、サブスクの便利さを本当の意味で享受できる社会。SubFiもそんな社会の一助になりそうだ。
山本 悠介
Yusuke Yamamoto株式会社 renue 代表取締役
東京大学を卒業後、アクセンチュア株式会社にて金融領域においてIT/戦略コンサルティングに従事。その後、複数のベンチャーにおいてマーケティング・広告運用の責任者を経験し、2021年にrenueを創業。