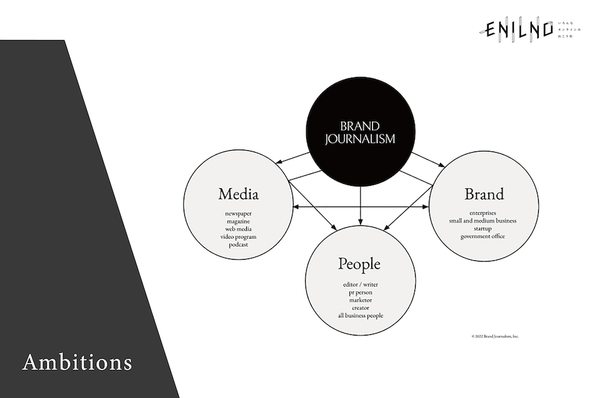ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。
これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。
1年で国公立大合格者を0から20名にした若き校長。学校のキャッチコピー「挑戦を、楽しめ」を地で行く重要性

もし自分が教職者で、ある日こう言われたらどうするだろうか。「きみが校長をやればいい」。ビジネスパーソンで例えるなら、「きみが社長をやればいい」と言われるものだろうか。
実際にそんな場面に直面し、校長を引き受けた若き先生がいる。全日制ではおそらく日本で初めての平成生まれの校長先生だ。しかもその校長先生は前年度は誰もいなかった国公立大合格者を1年で20名に増やすという実績も上げている。
そんな自身の実体験を記した著書「きみが校長をやればいい 1年で国公立大合格者を0から20名にした定員割れ私立女子商業高校の挑戦」を上梓した、福岡女子商業高等学校の柴山翔太校長に話を伺った。若き校長は、生徒たちとどう向き合い、いかにして改革し、そしてこの成果をあげたのか。
福岡県にある私立福岡女子商業高校はコロナ禍で大きな注目を浴びた。前年度まで一人もいなかった国立大合格者が、一気に20人に増加したのだ。立役者となったのは、2年前に赴任したばかりの国語科教員、柴山翔太氏だ。
「最初はオンラインで一人ずつ話をする機会を設けてもらったんです」と、柴山氏は1年目の苦労を語る。感染状況が悪化する中で、なんとか生徒の可能性を広げられないかともがく姿が、著書に記されている。
そもそも福岡女子商業高校には大学進学希望者が少なく、入学した時から就職するためのことを考えている生徒がほとんどだった。保護者は進学よりも早く就職してほしいと願っていたり、そもそも親自身が大学に通っておらず不便を感じていないため、子にも大学進学の必要性を感じていなかったりするケースが少なくない。
「九州という土地柄もあると思います」と柴山氏は言う。「特に教育においては、伝統を重視し、保守的な傾向があると感じます。『こうあるべきだ』という思いが強いんですね」(柴山氏、以下同)。実際、首都圏では女子生徒の方が大学進学率は高いが、九州では男子生徒が優位だという。
そんな九州の、しかも女子商業高校において、いかに生徒をやる気にさせるかというところから柴山氏の第一ステップは始まった。生徒へのヒアリングを続ける中で、「生徒に足りないのは自信と情報だ」と柴山氏は気づいたという。
もちろん大学に進学することが重要なことではない。ただ大卒と高卒の生涯賃金の差や、専門学校に行った場合と大学に行った場合の授業料の差といった情報が、生徒たちには欠けていた。柴山氏はこうした情報不足により生徒たちの可能性が狭まることを危惧していた。
そこで柴山氏は当時の校長に、学年集会で話す場を設けてもらうよう直談判した。壇上で語ったのは、「努力が最高の結果をもたらすとは限らない。だが、何もしない人がハッピーエンドを迎えることは絶対にない」ということ。この学年集会でのスピーチを機に、大学進学を目指す生徒が出てきたという。
変わる大学入試、重要視されるポイントの変化
そもそも柴山氏は前任の学校から小論文指導に当たってきた。小論文が進路指導と密接に関わっているのは、大学入試の変化によるところが大きい。かつて大学受験といえば学科試験が中心の一般入試の割合が高かったが、現在は約半数にとどまっている。その代わりに学校推薦型選抜ならびに総合型選抜が約半数を占めている。総合型選抜とはかつて「AO入試」と言われたものに近い。
こうした推薦入試や総合選抜入試においては、しばしば小論文の評価が高いウエイトを占める。だからこそ一般入試以外で大学を目指すなら、小論文は避けて通れないのだ。
ただし小論文の指導が難しいのは想像に難くない。「実はこの著書を書く前にも、本を書かないかというお話はいくつかいただいていました。ただそれらは『入試を突破するための小論文の書き方』といったテクニック的な内容のものだったので、違うかなと感じていました」。
実際、著書に記された柴山氏の指導を見ると、小論文は小手先のテクニックや一朝一夕で対応するには難しいのが理解できる。そもそも日本における小・中・高の学校教育の多くが、「決まった正解のある問題」で構成されている。一方で小論文に対しては正解がないことから、生徒たちは当初戸惑い、苦手意識を持つ。だからこそ柴山氏は小論文の指導に当たって、グループワークやディスカッションなどでまず「考える」「言語化する」というプロセスから始めている。

「数年前から教育現場は暗記型の学習から脱却してきているのを感じます。自分の頭で考え、意見を持ち、それを文章化できる生徒が求められる時代になっている。だから小論文の指導をするときも『これが正解です』という言い方はしない。さまざまな意見に対しても、『確かにそうかもしれないね』と生徒と一緒に考えていくこと、同じ土俵で話すことを大切にしています」。
柴山氏は生徒たちが「やらされている」という意識を持たないよう細心の注意を払っている。だからこそ生徒たちは徐々に小論文の面白さに気づいていく。小論文のテーマは現代社会における課題を扱うことが多く、そこで日本や世界について考えることは、高校生にとっても自分たちの暮らしに当てはまることが数多くあるからだ。
驚きの校長就任から最初に注力したこととは
柴山氏の丁寧な指導と、そして何より生徒の心に火をつけ続ける努力により、前年度0だった国公立大学合格者は、一気に20人になった。著書に描かれた合格発表のシーンはドラマチックで、『ドラゴン桜』『ビリギャル』といった教育をテーマにした作品の映像を彷彿とさせる。
1年目から華々しい進学率の上昇を果たした柴山氏だが、校長になる経緯は自身でも予期せぬものだった。学校の体制について理事長に4時間に及ぶ直談判をしたところ、最後に理事長から驚きの言葉が出たという。「きみが校長をやればいい」と。
着任してまだ日が浅く、しかも周囲には諸先輩方がいる中での突然の打診に、柴山氏は答えを逡巡したという。それを承諾したのは打診から2日後。若い世代が校長を務めることで、同じく若い教員を励ませるのでは、との思いが背景にあったという。
柴山氏が校長に就任してまず取り組んだことが、広報活動だった。福岡女子商業高等学校は当時、定員数の半数ほど、1学年100人足らずの生徒しかいなかった。生徒が少ないというのは、進路指導の面のみならず、経営面でも苦境にあった。だからこそ柴山氏は、積極的にメディアの取材を受けた。若き校長に就任したという話題性もあって取り上げるメディアも多く、「みましたよ」と声をかけられる機会が増加したという。
さらに平成生まれの校長の強みは、デジタルネイティブでありSNSに親しんで育ったことだ。教員の中にはSNSに慎重になる意見もあったが、それを振り切って生徒たちが主体となって広報活動を行う部活動「キカクブ」を承認した。
「キカクブではTikTokやInstagramの内容を生徒たちが企画し、撮影や編集も生徒たちが行います。商業高校だからこそ、こうした経験はデジタルマーケティングの実践の場、学びの場になると考えたのです」。
そこでキカクブの顧問となったのが、美容業界で経営コンサルタントとして仕事をしながらビジネスビューティーコースの授業を担当する特別非常勤講師。こうしたビジネスに通じた人材が教育現場に携わっているのも、私立の商業高校ならではかもしれない。この顧問の下、生徒たちはかなり専門的な他校分析も行った。
こうしてキカクブによって運営されているTikTokは、現在フォロワー3万人超、動画の中には850万再生を達成したものもある。「SNSをやって一番良かったと思うのは、知名度が上がったこと。それまでは中学生に『福岡女子商業高校って知ってる?』と聞いても誰も知らなかったのが、みんな名前を知ってくれるようになりました」。
学校の知名度の上昇は、そのまま数字に結びついている。令和2年度には定員割れの94名だった新入生が、令和5年度には217名に増加した。

急激に進んだ校務のDX化、挑戦は続く
この若き校長の挑戦は、教職員側にも変化をもたらしている。全国各地から教壇に立ちたいという志望者が集い、中には安定した立場の公立高校から私立高校の教員へと転じる人材もいるという。
あわせて推進しているのが、学校におけるDX化だ。ICTに強い教員を担当にし、その教員がうまく音頭をとったという。
「コロナ禍もあって、DXはものすごい速度で進みました。例えば校務支援システム『BLEND』を導入することで、以前は朝になると欠席や遅刻などの連絡のため電話が鳴りやまなかったのですが、それがなくなりました。ほかにも会議をなくして、代わりに議題をクラウドにあげたり、教員の間もチャットを使ったりと、DXによってかなり校務がスムーズになったと感じています」。
一般企業と同様の変革を、福岡女子商業高等学校では行っている。「学校だから」と切り離すのではなく、むしろ社会とシームレスにつながっていきたいと柴山氏は言う。
「高校や高校生ができることってまだまだあって、挑戦してみたいこともたくさんあります。今回本を書いたのも、生徒に挑戦をすすめている立場だからこそ、自分も挑戦しなければと思ったんです」。
変化を好まない土壌で、柴山氏は今日も改革の旗振りをする。福岡女子商業高校のキャッチフレーズは、「挑戦を、楽しめ」。何より校長先生が陣頭に立って、学びの場で挑戦を続けている。
柴山翔太
Shota Shibayama私立福岡女子商業高等学校校長
1990年北海道砂川市生まれ。 国語科の教師として4つの私立高校を経験後、同校に常勤講師として赴任。赴任1年目で進学指導、小論文教育により国公立大の合格者をゼロから20人に増やす。30歳で主任や部長職、教頭の経験もないまま校長に抜擢される。校長就任後はさまざまな学校改革を実施、生徒による新制服デザインや修学旅行プランニングなど新たな取り組みを行う。「きみが校長をやればいい 1年で国公立大合格者を0から20名にした定員割れ私立女子商業高校の挑戦」(日本能率協会マネジメントセンター)が初の著書となる。